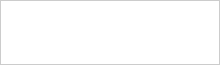森喜朗が安倍首相にサマータイム導入を進言したことで、その検討が開始された。
一般論として、サマータイムがオリンピック選手のためだけだとすると“労多くして功少なし”の感が否めない。国民にとってのメリットが明確でない状況では進めるべきではない。
では、ITコンサルの観点で、サマータイム導入の”労”を考えてみたい。
サマータイムで時刻を2時間早めてみるとする…サマータイムの開始日は、1日が22時間になる。この場合、時計を2時間早めることは容易だが、システムは24時間で設定されているため、この日に限っては、24時間内で終わらせる処理(仕事)を22時間以内で終わらせるようにしなければならない。スケジューリングや処理時間の検証に多大な労力を必要とする。
一方、サマータイム終了日はどうか、1日が26時間となる、1日は24時間ときまったことなので、延長された2時間の間に同じ時刻が2回発生することなる。これを解決するための手法の検討や、検討した手法の実施、さらには手法の確認試験に多大な労力を必要となるのである。
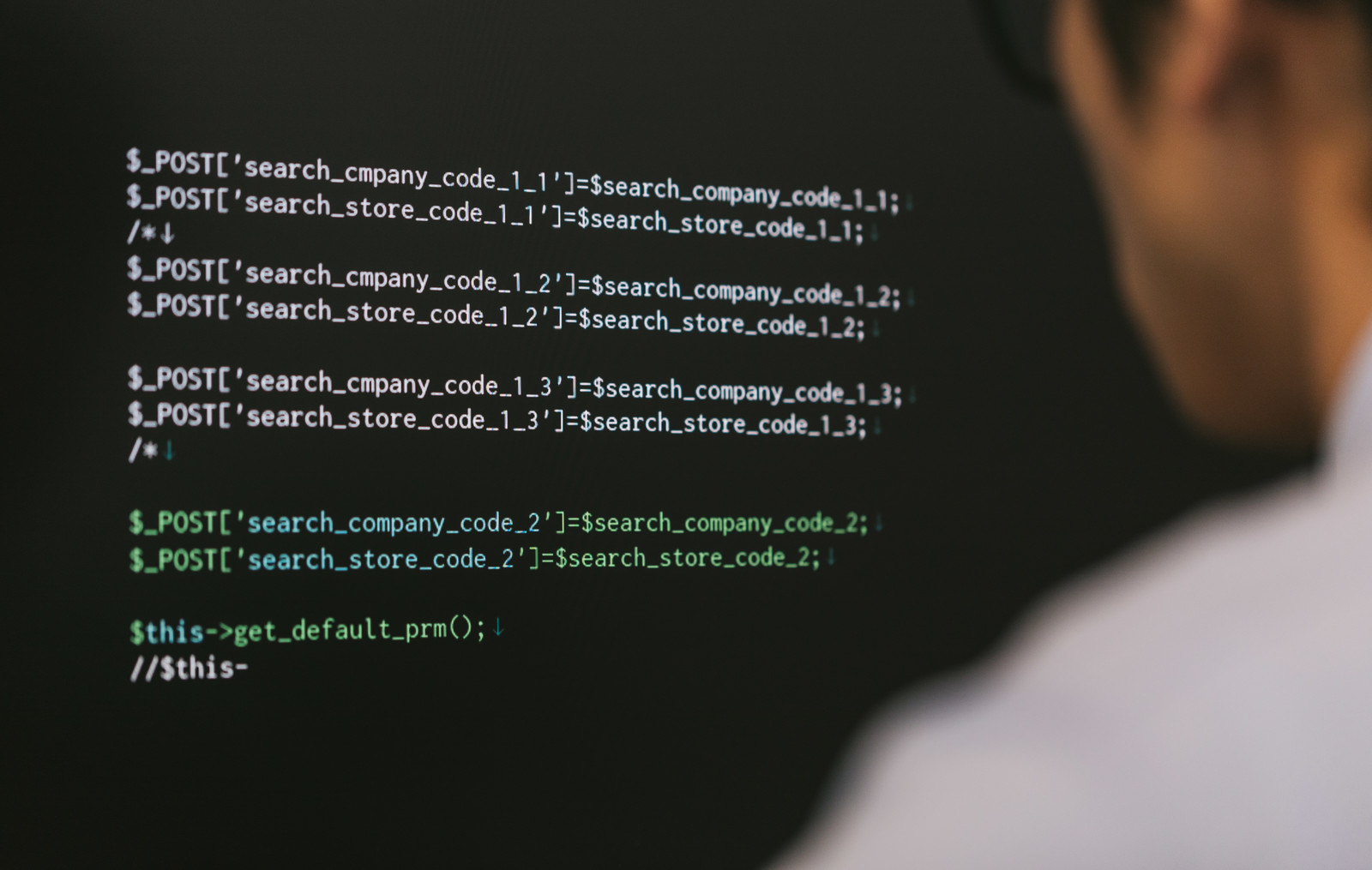
システムは想定していることにしか対処できない。サマータイムは想定外の仕様で、これに対応するためにはそれ相応の金と時間が必要となる。余談ではあるが、福島原発だって、想定外の事象には対処できず、膨大な金を投入しており、いまだに解決できていない。
時計の時刻を変えるだけじゃないかと思う方も多いだろうが、そんな簡単な話でないことが何となく分かってもらえると嬉しい。
個人的には、興味本位ではあるが日本でサマータイムを導入したらどうなるのかを見てみたいと思っている。ちなみに、EUでは省エネ効果がないとし、サマータイムの見直しが始まったとのこと。